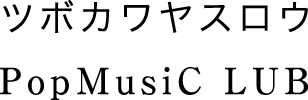実家に帰った際、久しぶりに坂本龍一さんの初期のアルバムが聴きたくなり、1st.「千のナイフ」から順番に聴きました。多分、最近の自曲「散歩」「楽しいひととき」で、坂本さんの音源をサンプリングして使用している事もあってではないかと。
その「散歩」に「+パントナル」のビートを使用した際、「+パントナル」が収録されているアルバム「キャズム」(‘04年) について、当ブログにこう書いています。
… ’90年代の一連のアルバムを括弧で括って、’80年代のご自身の音楽から繋げたような音で (←ファン以外には分からないと思うけど…)、当時けっこう聴き込みました。
という訳で、初期のアルバムを聴き返しての所感を。

上から順番に「千のナイフ」「B-2 ユニット」「左うでの夢」、12インチ・シングル「ジ・アレンジメント」。
どこまでが初期と括るかは人それぞれですが、私は3rd.アルバム「左うでの夢」(‘81年) までとしたいです。初期というとざっくりし過ぎているので、第1期という方が合ってるかもしれません。このアルバムの次に「M」のロビン・スコットとの共作12インチ・シングル「ジ・アレンジメント」(‘82年) 、サウンドトラック「戦場のメリークリスマス」(‘83年) がリリースされますが、この辺から、次のステージに移った感がします。
次のステージというのは、「戦メリ」「音楽図鑑」の数曲に代表される、坂本サウンドの大きな特徴であるロマンティシズム溢れるメロディ、にストレートに向き合った楽曲群、です。この辺で己れの資質に自覚的になり?大きくブレイクした感がします。(ブレイクと言っても大して売れていませんが)
「左うでの夢」までは、ロマン気質をストレートに表現するのを意図して避けていたように思えます。多分、単純に気恥ずかしかったのではないかと。その証拠?に、他人のアレンジ (大貫妙子さんなど) では、やり過ぎなくらいにリリカルです。特に大貫さんのアルバムは、アルバム・コンセプト上、大っぴらにご自身のロマンティシズムを発揮出来たのではないかと。
私が最も好きでよく聴いていたアルバムは、1st.アルバム「千のナイフ」(‘78年) です。
このアルバムはYMO前夜にひっそりとリリースされています。私は多くの方と同様に、YMOブレイク後にこのアルバムを聴いたのですが、はっきり言ってYMOよりもショックを受けました。
ここで鳴らされる、ニヒリズムに溢れていて、幾何学的で整然としていて、それでいて脱構築な音は (←比喩が多すぎ 笑)、当時よく聴いていたゲイリー・ニューマンその他、イギリスのシンセ系ニュー・ウェイヴの音と世界観に、ピッタリとシンクロしました。2nd.アルバム「B-2 ユニット」(‘80年) もそうです。(「B-2 ユニット」の方が「千のナイフ」よりもイギリス寄りです。正直言って、高校1年当時は完全に理解出来ない音でした)
ニヒリズム溢れたとは言ってもそれは当時の印象で、今聴きかえすと、不安定なメロディの中に、時折点在するリリカルさは、断片的ですが「戦メリ」以降を内包しています。
ストレートにロマンティックな「戦メリ」「音楽図鑑」「未来派野郎」、ワールド・ミュージックにアプローチした「ネオ・ジオ」「ビューティ」、そしてそれ以降の’90年代の作品群に比べると、あまりにも個人的で儚い響きは、この時期ならではのものです。
機会があったら、1枚ずつ語ってみたいです。

1番よく聴いた「千のナイフ」。その中でも特によく聴いた、タイトル曲を聴きながら。
(追記)
その初期のアルバムの合間に、シングル盤を2枚、リリースしています。そのうちの1枚「フロントライン」(‘81年) のB面曲に、YMOでもセルフ・カバーしていた隠れた名曲「ハッピー・エンド」が収められています。リリカル且つ虚無感溢れている曲で、当時はこれぞ坂本龍一節だと、大いに感動してリピートしていました。
時は動いて’21年。ロックバンド、SEKAI NO OWARI が、この曲メロをビートに乗せてラップする曲「Like a scent」をリリースしました。その声があまりにもリリカルでデジタルな曲メロにハマっていて、CDまで購入して毎日リピートしていました。Fukaseさんの儚い声と殺伐としていながらも希望を謳うリリックが、初期の坂本龍一さんの世界と完全にダブって聴こえました。
坂本さんの初期の楽曲群は、今の時代にも十分刺さる力があると、その時感じたものです。

SEKAI NO OWARI「セント・オブ・メモリー」。