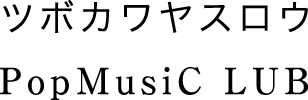先日の芥川賞の受賞作「東京都同情塔」について、作者の九段理江さんがインタビュー中の「AI時代に小説を書く意味はどう考えているか」という質問に対して、このように答えられていました。
「今回の小説に関しては、だいぶAI、つまりチャットGPTのような生成AIを駆使して書いた小説でして、おそらく全体の5%くらいは生成AIの文章をそのまま使っているところがあるので。これからも利用しながら、かつ利用しながらも自分の創造性を発揮できるように、うまく付き合っていきたいと考えています」(記事より抜粋)
音楽や映画、アニメ等だと既に当たり前になっている生成AIの利用です。文学に使用されるのも別におかしな事ではないと、私は思うのですが、文学好きの方々からは非難轟々みたいです。
幾つかの記事のコメント欄を読んでいて、私が中学生〜高校生の頃に登場したYMO (イエロー・マジック・オーケストラ) が、大人の音楽ファンや評論家に「機械に演奏させるなど音楽ではない」的な、的外れな批判が噴出していた事を思い出しました。
綿矢りささん以来、芥川賞受賞作を読んでいませんでしたが、今回の「東京都同情塔」、久しぶりに読んでみたくなりました。そういえば綿矢りささんも九段理江さんも、女性ですね。女性の方が頭が柔らかいのかな?と短絡的にふと思った途端、いや、すぐそうやって性差に結びつける事こそが、頑固な男性的ステロタイプな思考に陥っているんだよな、などと思ったり。